Windows 10では回復ドライブというバックアップ方法が提供されたため、小さなパソコンメーカーは工場出荷状態に戻す手段を提供しなくなりました。
しかし、回復ドライブでは完全に元の状態に復元することはできません。
Windows 10の回復ドライブ
Windows 7では、Image Xというバックアップ方法が提供されていました。
これは指定したストレージについてアプリケーションも含めてすべてのパーティションのバックアップを取るもので、サードパーティから提供されるイメージバックアップソフトと大きな違いは無いものでした。ただし、すべてのファイルをバックアップするため、大きなバックアップストレージを必要としました。
それに代わるものとしてWindows 8では、回復ドライブというシステムだけをバックアップする機能が搭載されました。
クラウドにデータを置くことが主流となった現在では、システムだけバックアップすれば十分と考えてのものでしょう。
そしてWindows 10に搭載された回復ドライブは更に進化したものとなり、常に最新のシステムをバックアップし、しかも、インストールされているWindows 10から回復イメージを作成するため、大きな回復パーティションを必要としなくなりました。
回復ドライブで復元できるもの
今回購入したLIVA-C0-2G-32G-W10というパソコンも、工場出荷イメージは付いておらず、何かしらの方法でバックアップを取らなければ購入時の状態に戻せないものでした。
そのため、Windows 10の回復ドライブを作成してバックアップを取り、正しく復元できるか試してみました。
こちらが購入時のSSDの状態です。
そしてこちらが回復ドライブで復元した状態です。
パーティションの順番も正しく問題無いように見えますが、回復パーティションのサイズが1GBから450MBに変わっています。450MBとはWindows 10のデフォルトの回復パーティションサイズです。
このことから回復ドライブでは回復パーティションのサイズは保存されないことが分かります。
回復パーティションは450MBになっても問題無いと思われるかもしれませんが、元々1GBだったことには理由があります。
Windows 10は半年ごとに大型アップデートを繰り返しますが、それまでの利用状況によっては回復パーティションが450MBでは足りなくなる場合があります。
その場合、既存の回復パーティションは使わずに、この例のように新たに回復パーティションが作成されてしまいます。
SSDの容量が小さいパソコンでは、繰り返し追加される新たな回復パーティションは容量不足の原因となります。
そのため予め回復パーティションを1GBなど大きめにしておくことは、今後のアップデート対策として有効です。
ここでは既存の回復パーティションサイズを変更する方法を説明します。
回復パーティションサイズの変更方法
この記事では手動での回復パーティションサイズの変更方法について説明しています。しかし、より簡単にサイズを拡張する方法についてはこちらの記事を参考にしてください。対話形式でサイズ変更できるスクリプトをダウンロードできます。

拡張しかできませんので縮小したい場合は、この記事の手順で操作してください。
注意事項
回復パーティションは通常のデータパーティションと異なり、パーティション操作ソフトでは操作できない場合があります。
ここで使用するEaseUS Partition Master Freeは、回復パーティションも操作できるのですが、操作後にデータパーティションに変更されてしまうため、コマンドで回復パーティションに戻す必要があります。
また、ここで対象とするのは回復パーティションがWindowsシステム(Cドライブ)の後にある場合とします。
Windowsシステムより前にある場合も変更できるのですが手順が異なるのでクリーンインストール時に事前に作成する方法で説明しています。
EaseUS Partition Master Freeのインストール
まず、こちらからパーティション操作ソフトをダウンロードしてインストールします。
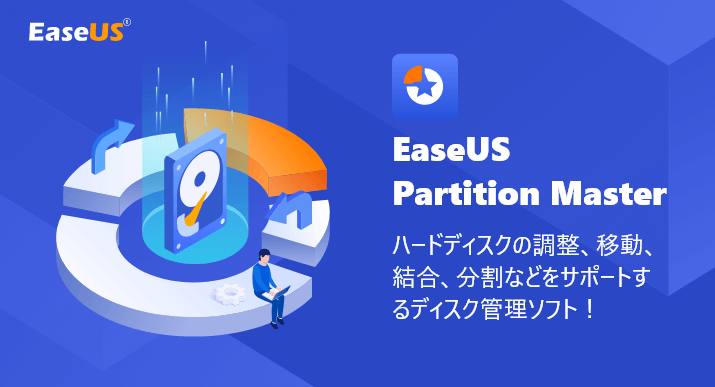
有償版や他社の同様なソフトでも構いませんが操作が異なりますので、適宜読み替えてください。
また回復パーティションを操作できないソフトでも、コマンドでデータパーティションに変更することで操作できるようになります。
回復パーティションの種類と属性を保存
デスクトップの何も無いところで右クリックし「新規作成」「テキストドキュメント」をクリックして

デスクトップにテキストファイルを作成します。名前は何でも構いません。
作成したらダブルクリックして開いておきます。

[Windows]+[X]で表示されたメニューから「コマンドプロンプト(管理者)」をクリックします。
PowerShellが表示される場合はスタートメニューの「Windowsシステムツール」から開いてください。

「diskpart」を起動します。
- list disk
でシステムドライブのディスク番号を確認します。この例では「0」です。
- select disk 0
でディスクを選択します。「0」はシステムドライブの番号です。
- list partition
で回復パーティションのパーティション番号を確認します。この例では「4」です。
- select partition 4
でパーティションを選択します。「4」は回復パーティションの番号です。
- detail partition
で回復パーティションの詳細情報を表示させます。
表示された情報の先頭をマウスでクリックしたままドラッグして選択します。
[Enter]、または[Ctrl]+[C]でクリップボードにコピーします。
開いておいたテキストファイルにペーストしてから、ファイルを閉じて保存します。
EaseUS Partition Master Freeでのパーティションサイズ変更
EaseUS Partition Master Freeを起動します。
手順としてはWindowsシステムパーティションを前に縮小し、空いた後の部分を使って回復パーティションを拡張します。
Windowsシステムパーティションを選択して「パーティションのサイズ調整」をクリックします。
後を空けますので、前側の未割当領域は0MBのまま、パーティションサイズを減らしていきます。
回復パーティションを1GB(1024MB)とする場合、後側の未割当領域は、
- 1024MB - 450MB = 574MB
なので574MBに近い値となるように調整します。
設定したら「OK」をクリックして閉じます。
左上の「チェック」をクリックして変更を適用します。
他のすべてのソフトを終了させて再起動できる状態にして「はい」をクリックします。

「はい」をクリックして再起動します。

再起動してパーティションサイズが変更されるとサインイン画面になりますので、サインインしてEaseUS Partition Master Freeを起動します。
次に回復パーティションのサイズを変更しますので「Windows RE tools」とあるパーティションを選択して「パーティションのサイズ調整」をクリックします。
前後の未割当領域を0MBにし、パーティションサイズを最大にして「OK」をクリックします。
左上の「チェック」をクリックして変更を適用します。
今回はシステムパーティションではないので再起動はされません。
「はい」をクリックして変更を適用します。

回復パーティションサイズが変更されるのを待ちます。
変更が適用されましたので「OK」で閉じます。

これでパーティション操作は終了なのでEaseUS Partition Master Freeを終了させます。
ただし「ディスクの管理」で確認すると「回復パーティション」はサイズは変わっていても「データパーティション」に変わってしまっているので「回復パーティション」に戻す必要があります。
回復パーティションの種類と属性を復元
先ほどと同じ手順で「コマンドプロンプト(管理者)」を起動します。
「diskpart」を起動します。
ディスク番号、パーティション番号は変わっていませんので、先ほどと同じ手順で、
- select disk 0
- select partition 4
- detail partition
と実行します。
先ほどデスクトップに保存したテキストファイルと比較すると「種類」と「属性」が変わってしまっていることが分かります。
以下のように実行して「種類」と「属性」を直します。
コマンドはこのページからコピーアンドペーストしてもよいですが、テキストファイルからコピーアンドペーストする方が早いでしょう。
コマンドプロンプトでは右クリックでペーストできます。
- set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
- gpt attributes=0x8000000000000001
これらを実行したら、
- detail partition
で確認してください。
- exit
でdiskpartを終了し、コマンドプロンプトを閉じます。
[Windows]+[X]で表示されるメニューから「ディスクの管理」を起動すると回復パーティションサイズが正しく変更されていることを確認できます。
初期化
工場出荷状態に戻す場合は、EaseUS Partition Master Freeがインストールされている状態は好ましくないので、「設定」アプリの「更新とセキュリティ」「回復」「このPCを初期状態に戻す」で初期化してください。
「このPCを初期状態に戻す」を行っても回復パーティションのサイズは変更されません。
まとめ
回復ドライブによるバックアップは、あまり使い勝手がよくありません。
そうは言っても、Windows PEやLinuxベースのバックアップソフトを立ち上げてバックアップするにはUSBポートが不足することもあり、回復ドライブを使わざるを得ない場合もあります。
回復ドライブの特性をよく知って活用してください。
また、ここに記した方法で回復パーティションサイズを予め変更しておけば今後のアップデートで回復パーティションを増殖させなくて済みます。






































コメント